大学の教員として
多くの「未知」が潜む、量子情報の基礎研究に取り組む
-
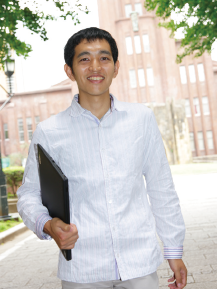
東京大学大学院 理学系研究科 助教
添田彬仁さん2002年春、物理学関連コース入学。2006年、東京大学大学院に入学、2011年修了、博士号取得。その後2年間、シンガポールの研究所で研究。2013年、東京大学大学院・村尾研究室(量子情報)に戻り、助教として研究を続けている。
メッセージ
「量子論」の分野は研究の歴史が浅く、未解明な部分が数多くあります。例えば、量子論を導入すると情報処理能力が驚異的に上がり、現在のコンピュータでは不可能または膨大な時間を要する因数分解を簡単にできることは分かっているのですが、それが何故なのかは解明されていません。
私の研究の研究テーマは、量子ビット(量子情報の最小単位)2つで「何ができるか」を理論的に解明し、将来の量子コンピュータにつなげようというもの。道のりは険しいのですが、多くの「知」が潜んでおり、やりがいはあります!
先進科学プログラムの入試制度(現、方式Ⅰ)は、私のように文系が苦手な人にとってたいへん魅力的でした(笑)。一方、入学後は一般の学生より多くの授業が待ち構えているので、勉強は決して楽ではありません。しかし、1年次から教授の個人指導が受けられ、専用の学習室まで用意されているなど、多くのメリットもあります。飛び入学は、標準ルートではないかもしれませんが、少し違った世界を見たいと思える人には絶対にオススメ。1年早く入学できれば、その後の人生でも1年分の余裕を持って生きられるので、精神的に大きなアドバンテージです。